「風営法って難しい」「改正で何が変わったの?」
そんな疑問を持つ方のために、この記事では2025年(令和7年)の風営法改正を、施行日ごとに分けて詳しく解説します。
特に今回は、
- 6月28日施行分(営業ルール・罰則の強化)
- 11月28日施行分(欠格事由の拡大・法人単位の責任)
の2つの改正内容があり、それぞれで目的と対象が異なります。
行政書士などの専門家の現場でも注目されている重要な改正ですので、わかりやすく説明していきます。

改正の背景 ― なぜ今、風営法が変わったのか?
近年、ホストクラブやキャバクラを中心とした「接待飲食営業」で、深刻なトラブルが増えています。
たとえば…
- お客が高額な「ツケ(売掛金)」を抱えて返済不能になり、風俗で働かされる
- 「恋愛感情」を利用して飲食を強要される
- 名義貸し・無許可営業による違法経営が横行している
こうした事例は「経済的DV」として報道されることもあり、社会問題化しました。
この流れを受けて警察庁は、風営法を抜本的に見直し、
「悪質業者を排除し、真面目に営業するお店を守る」ことを目的に改正を行いました。
施行日は2段階!6月と11月で内容が違う
2025年の改正は、次のように2回に分けて施行されています。
| 施行日 | 主な改正内容 |
|---|---|
| 令和7年6月28日 | 営業ルール(遵守事項)の明確化、禁止行為の追加、罰則強化、スカウトバック禁止 |
| 令和7年11月28日 | 許可の欠格事由の拡大、関連法人や親会社単位での責任追及 |
つまり、6月改正は「現場のルール強化」、
11月改正は「経営者・法人責任の強化」がメインとなっています。
令和7年6月28日施行分 ― 営業ルールの明確化と罰則の強化
6月に施行された内容は、「接待飲食営業のルールを明確化し、悪質な勧誘を取り締まる」ことが中心です。
ここでは、営業の“中身”に直接関わる改正が行われました。
① 「接待飲食営業」の遵守事項が明確化
まず明確になったのが、営業中に守るべき「遵守事項」です。
具体的には、次のような行為が禁止されます。
- 利用料金について虚偽の説明をする
- 客の恋愛感情などに乗じて飲食を要求する
- 客が注文していない飲食物を勝手に提供する
具体例
- 「初回1時間3,000円」と説明しておきながら、退店時に10,000円請求する
- 「あなたが好きだからシャンパン入れて」と心理的に迫る
- 客が頼んでいない高額ボトルを勝手に開ける
これらはすべて違反行為となり、指導・処分の対象になります。
② 禁止行為の追加と刑事罰
これまでは「グレーゾーン」とされていた一部の行為が、今回の改正で明確に違法行為と定義されました。
禁止された行為
- 客に威迫・困惑を与えて注文や支払いをさせること
- 売掛金返済のために売春・風俗勤務・AV出演を強要すること
想定される事例
- 「払えないなら身体で払え」といった強要
- 売掛返済を口実に他店や風俗に斡旋する
- 「返済しないと警察に言うぞ」と脅す
これらに違反すると、6か月以下の拘禁または100万円以下の罰金が科されます。
また、経営者だけでなく接客従業員も罰則対象になります。
③ 無許可営業の罰則強化
風営法に基づく営業許可を受けずに営業した場合、以前は軽い罰則でした。
しかし6月の施行では個人・法人ともに大幅な引き上げが行われました。
| 区分 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 個人 | 2年以下の拘禁または200万円以下の罰金 | 5年以下の拘禁または1,000万円以下の罰金 |
| 法人 | 200万円以下の罰金 | 3億円以下の罰金 |
無許可で営業を行うことは、もはや「軽い違反」ではなく、重大な犯罪行為とみなされます。
現場の例
- 営業時間を誤って申請し、実質的に「深夜接待営業」状態になっている
- 許可を取らずに「ホステスを置く形態」で営業している
- 名義貸しで他人の許可を利用して営業している
いずれも摘発の対象となる可能性があります。
④ 性風俗店のスカウトバック禁止
性風俗関連営業(ソープランド、デリヘル、出張サービスなど)が、
スカウトや紹介業者に「紹介料」を支払う行為も禁止されました。
背景
スカウト行為を通じて女性を不当に労働させ、売掛金の返済に充てさせるといった搾取的構造が問題視されました。
たとえば…
- スカウトが紹介した女性が働き、紹介者が報酬を受け取る
- 実質的に人身売買に近い形になっているケース
こうした構図を断ち切るために、「スカウトバック禁止」が法制化されました。

令和7年11月28日施行分 ― 欠格事由の拡大と法人責任の明確化
11月施行分は、経営者・法人レベルでの責任を強化する改正です。
つまり、6月施行が「お店の中のルール」だったのに対し、11月施行は「経営者の資格や法人全体の信頼性」に関わる部分です。
① 欠格事由(許可を受けられない条件)の追加
新たに、以下のような事業者や法人は許可を受けることができないことが明文に盛り込まれました。
| 新しい欠格事由 | 具体的な内容・例 |
|---|---|
| 親会社・子会社が許可取り消しから5年を経過していない | グループ企業内で過去に違反があると新規申請不可 |
| 警察の立入調査後に許可証を返納してから5年を経過していない | 指導・監督逃れの返納も処分対象に |
| 暴力団関係者などが実質的に経営に関与している | 名義上は別会社でも、実質的支配がある場合はNG |
具体例
- 親会社が風営許可を取り消されたスナックが、子会社名義で再申請 → 不許可
- 立入検査の直前に許可証を返納したバー → 再申請しても5年間は許可が出ない
- 過去に暴力団関係者が出資していたキャバクラ → 実質的関与と判断されれば不可
② グループ企業単位での責任追及
今回の改正のポイントは、個人単位ではなく法人グループ単位で責任を問う点にあります。
たとえば、ホールディングス形式で複数店舗を経営している場合、
1店舗で許可取り消しが発生すると、他店舗や関連会社の新規申請にも影響が出る可能性があります。
このため、グループ内でのコンプライアンス体制(法令遵守の仕組み)が非常に重要になりました。
③ 11月改正における実務上の影響
- 許可申請書の添付資料として、関係法人の一覧・経営関与状況の説明が求められる場合があります。
- 法人登記簿や株主名簿などを提出し、関係者の確認を受けるケースが想定されます。
- 実質的に「透明性の高い経営体制」がないと許可が通りにくくなる可能性があります。

改正に対応するために営業者がすべきこと
風営法改正に対応するためには、「現場」+「経営」両面の見直しが必要です。
① 現場対応(6月施行分)
- スタッフ全員に遵守事項と禁止行為を周知
- メニュー表・料金表示を改訂し、誤解を招く表現を排除
- トークマニュアルから「恋愛感情を利用する表現」を削除
- 接客中の会話トラブルを防ぐため、教育資料や録音ルールを整備
② 経営体制の見直し(11月施行分)
- 親会社・関連会社・取引先を含む許可履歴のチェック
- 名義貸し・実質支配の有無を整理
- 株主・役員構成を透明化し、暴力団関係者との関係遮断
- 立入調査時の対応マニュアルを作成
③ 行政書士など専門家の活用
行政書士に依頼すれば、
- 許可申請・届出書類の作成
- 図面(営業所平面図)の作成・修正
- 警察署への事前相談・書類提出代行
まで一貫してサポートしてもらえます。
自分で対応するよりも確実で、後のトラブルを防ぐ意味でも安心です。
まとめ ― 改正は「ルール」から「責任」へ
2025年の風営法改正は、
- 6月改正で「営業現場のルール」を厳格化
- 11月改正で「経営者・法人の責任」を拡大
という二段階構造になっています。
つまり、「何をしてはいけないか」だけでなく、
「誰が責任を取るのか」まで問われる時代になったということです。
今後は、誠実な営業・透明な経営を続けることが、
お店の信頼を守る最大のポイントになります。
あおい行政書士事務所
行政書士 中村佳織
神奈川県在住。高校生と中学生の二児の母。最近子どもの反抗期に参っていて、己の精神力アップの修行中。
趣味はサウナ・岩盤浴、そしてラーメン巡り。
お酒好き。柴犬のぽん(♀)に毎日癒されてます。

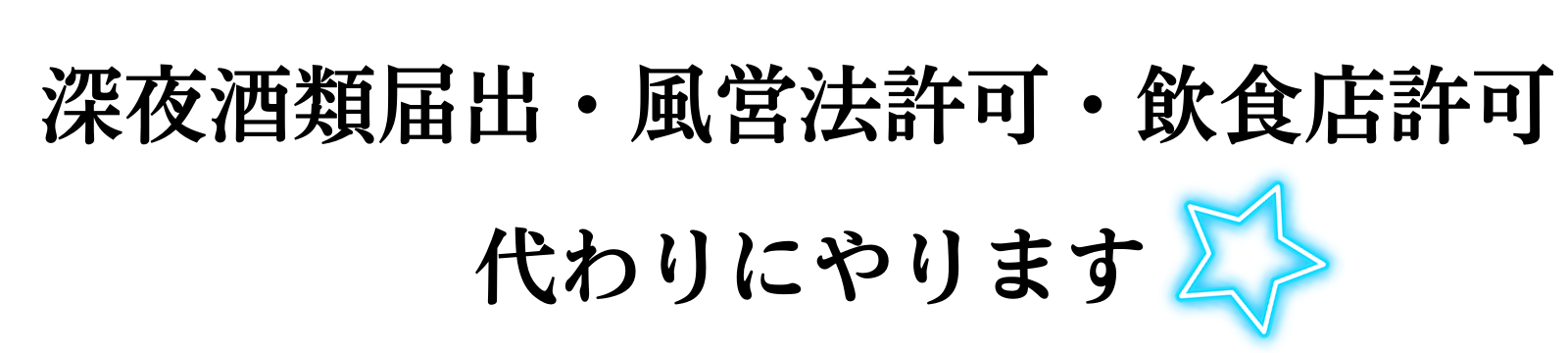
コメント